障害という概念は、個人の「中」にある能力や機能の問題だと捉える「医学モデル」から、社会環境との「間」のミスマッチだと捉える「社会モデル」へと移行しつつあると言われています。障害とは何かを考えることで、社会の中で「当たり前」だと見なされていることが浮き彫りになるのではないでしょうか。
他方、今後社会生活の基盤として発展することが期待されている「メタバース」。障害が人と社会環境の「間」にあるのであれば、メタバースの設計は、そのまま障害を定義することに繋がりうるかもしれません。
今回、Mogura VR Newsでは「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」(以下、分身ロボットカフェ)を運営する株式会社オリィ研究所CEOの吉藤オリィ氏と、「当事者研究」を推進されている東京大学准教授の熊谷晋一郎氏をお招きし、メタバースと障害をテーマにした対談を行いました。
オリィ氏による「分身ロボットカフェ」は、外出困難者である従業員がロボット「OriHime」をアバターとして遠隔操作することで、配膳や接客等のサービスを実現している常設の実験店です。そして当事者研究は、何らかの困りごとを抱えている当事者が、自己と社会や他者との「ズレ」を仲間と共に自ら探究する営みです。
テクノロジーによって障害という概念を更新し続けているオリィ氏と、当事者の目線から障害の正体を記述する熊谷氏に、誰ひとり取り残さない世界をつくるために必要なことは何か、そしてメタバースが「障害」という概念をどのように変えるかについて議論していただきました。

吉藤オリィ / Ory Yoshifuji
1987年、奈良県生まれ。株式会社オリィ研究所 代表取締役所長。小学校5年から中学校2年まで不登校を経験。高校時代に電動車椅子の新機構の発明を行い、国内最大の科学コンテストJSECにて文部科学大臣賞、世界最大の科学コンテストIntel ISEFにてGrand Award 3rd を受賞、その際に寄せられた相談と自身の療養経験から「孤独の解消」を研究テーマとする。早稲田大学にて2009年から孤独解消を目的とした分身ロボットの研究開発を独自のアプローチで取り組み、2012年株式会社オリィ研究所を設立。分身ロボット「OriHime」、ALS等の患者さん向けの意思伝達装置「OriHime eye+ switch」、全国の車椅子ユーザに利用されている車椅子アプリ「WheeLog!」、寝たきりでも働けるカフェ「分身ロボットカフェ」等を開発。米Forbes誌が選ぶアジアを代表する青年30人「30 Under 30 ASIA」、2021年度の「グッドデザイン賞」15000点の中から1位の大賞に選ばれる。書籍『孤独は消せる』『サイボーグ時代』『ミライの武器』。オリィの名前の由来は趣味の折紙から。

熊谷晋一郎 / Shinichiro Kumagaya
東京大学医学部医学科卒業後、千葉西総合病院小児科、埼玉医科大学病院小児心臓科での勤務、東京大学大学院医学系研究科博士課程での研究生活を経て、東京大学先端科学技術研究センター准教授、小児科医。東京大学バリアフリー支援室長。専門は小児科学、当事者研究。1977年生まれ。新生児仮死の後遺症で脳性まひになる。高校までリハビリ漬けの生活を送り、歩行至上主義のリハビリに違和感を覚える。中学1年時より電動車椅子ユーザーとなる。高校時代に身体障害者の先輩との出会いを通じて自立生活運動の理念と実践について学び、背中を押されて大学時代より一人暮らしを始める。大学時代に出会った同世代の聴覚障害学生の運動に深く共鳴する。「見えやすい障害」をもつ自分への「排除型差別」とは異なる、「見えにくい障害」に対する「同化型差別」の根深さを知る。主な著作に、『リハビリの夜』(医学書院、第9回新潮ドキュメント賞)、『当事者研究――等身大の〈わたし〉の発見と回復』など。
障害との関わり
——本日はよろしくお願いいたします。まずは、お二人がそれぞれ「障害」というものにどのように取り組み、どのような関係を築いてきたか、自己紹介を兼ねて教えてください。
吉藤オリィ(以下オリィ):
私は「OriHime」というロボットを作っており、それを使って「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」という常設の店舗を運営しています。現在では70人程の仲間達と一緒に、そこで「寝たきりの先へ行く」ための研究をしています。
私は「障害」のことを広く「自分がやりたいと思ったことの実現を阻むハードル」だと考えています。例えばパーティに招かれたけれど、遠方で仕事をしているから参加できないという人は、「行きたいのに行けない」という意味において、身体的な障害を持っているのとあまり変わりません。だからOriHimeのことを「心の車椅子」と呼ぶこともあります。
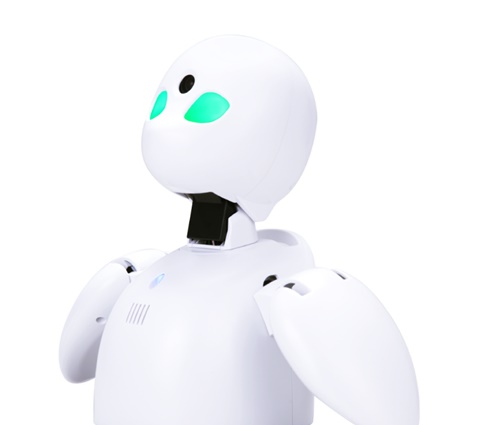 |
 |
(分身ロボットOriHime(左)と分身ロボットカフェDAWN ver.β(右)。2019年より実証実験を繰り返し、2021年には常設店を構えた「分身ロボットカフェ」は、文化庁メディア芸術祭第24回エンターテインメント部門ソーシャル・インパクト賞を受賞している)
オリィ:
私自身にはいわゆる「身体障害」があるわけではありませんが、身体は昔からあまり強くありません。そのため小学校の頃は学校にあまり通えず、不登校や引きこもりを三年半ほど経験し、十九歳まではあまり人前で話すことができませんでした。人の顔を見て話すことは、正直今でも苦手です。
昔から身体が弱かったこともあり、車椅子には興味がありました。高専時代には「もっとかっこいい車椅子を作りたい」と思って開発をしていました。
10年ぶりに母校の王寺工業高校を訪問。当時作った「絶対に傾かないクールな車椅子」、未だにエントランスに展示してもらえいて、10年ぶりに電気を流したらちゃんと回路が生きてて水平制御装置が機能したのは感動的だった。やっぱりものづくりは丁寧につくらなあかん。 pic.twitter.com/dx4jL9ZubX
— 吉藤オリィ@寝たきりの先をつくる (@origamicat) July 31, 2017
オリィ:
車椅子をはじめとするさまざまな開発を通じて、今まで自分では「できない」と思っていたことが「できる」に変わった瞬間、人が前向きに変わっていく様子を何度も見てきました。生活が豊かになることや便利になることももちろん大事ですが、誰かに必要とされたい、自分がいることで誰かの役に立てば嬉しいという思いは、誰にでもあるものです。
そんな気づきを経て、これまで寝たきりの——私は彼らのことを寝たきりの「患者」ではなく、「先輩」と呼んでいますが——先輩たちとともに、どうすれば「自分」をもう一度信じられるようになるのか、もう一度自分が世の中から必要とされていると感じられるのかを日々考えています。そういった背景もあって、「分身ロボットカフェ」を開いています。
熊谷晋一郎(以下熊谷):
私は「障害者」というカテゴリーを社会から付与される身体を持って生まれ、生きてきました。障害や障害者という言葉の中に含まれる、目に見えて分かりやすい特徴の身体。それが私と障害との最も長い関わりです。
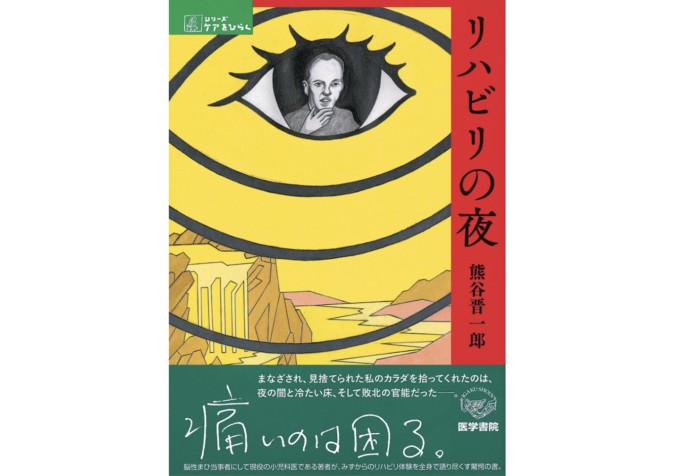
(熊谷氏の著書『リハビリの夜』)
他方で、紆余曲折の末に医学という領域で学び、小児科医として障害や病気を持った方をサポートする側にも回りました。二十四歳ぐらいから携わってきた医者という職業が、私と障害の二つ目の関わりです。
そしてさらに、三十歳ぐらいからでしょうか。今度は研究という形で、障害や病気について携わる立場になりました。そのアプローチが「当事者研究」です。
私はそれまで、自分自身が当事者であるということと、障害を持つ人の支援を医療者として実践していること、この二つの経験の間に距離を感じていました。私自身も生き延びるためのさまざまな知恵を、当事者の先輩からも、医学的な知識の系譜からもいただいてきましたが、この両者が混ざり合っていないような心地がしたのです。当事者としての一人称的な体験と、医学の三人称的な視点。どちらか一方に吸収されるのではない形で、両者に橋をかける実践はないだろうかと考えていました。
そんな時に出会ったのが「当事者研究」です。当事者性を大切にしながら研究をするという試みが、日本の中で、特に精神障害の領域で誕生していることを知り、それ以来ライフワークとして取り組み続けています。
知っている「誰か」のためのテクノロジー
——メタバースについての話題よりも先に、既存のテクノロジーと障害の関わりについて伺いたいと思います。これまでにもさまざまなデバイスやアプリケーションが普及してきましたが、これらは障害者にどのように受け止められ、使われてきたのでしょうか。思い当たるエピソードなどがあれば教えてください。
オリィ:
まず思い出すのが、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の方が現地の人とお花見を一緒に楽しめるように、OriHimeを使って頂こうとした時のことですね。その時に分かったのが、当時のOriHimeは、ALS当事者が自ら操作できるようなものではなかったということ。なにしろOriHimeの出発点は「不登校だった私が学校に通うためのツール」でしたから。
そこで「じゃあどうすればALSの方でも操作できるのだろうか」と考えて、筋電による制御などのさまざまなプロトタイピングを行いました。最終的には、当時まだ一般的ではなかった視線入力の方法に行き着き、今ではOriHimeのみならず、文字入力を筆頭にWindows PCの操作を全て行うことのできる「意思伝達装置」にまで発展しています。
(視線入力やスイッチ入力で文字入力や合成音声でのスピーチができる意思伝達装置「OriHime eye+Switch」)
このシステムが進化したきっかけは、「知っている人の困りごとを解決したい」という意志です。私はOriHimeというロボットを作った時、最初からあらゆる人々に適用できるモノにしようと考えていたわけではありませんでした。まずは「とにかく自分が使いたいもの」。そして私と同じく不登校で悩んでいる子が学校に行けるようにすることを目的にしていました。そして仲良くなったALSの人たちにも使ってもらいたいと思うようになり、新しい装置が生まれたのです。そうしたら今度は、「ALSの人たちだけずるい」と言われるようになったりもして。
分身ロボットカフェの仲間にもいろいろな病気を持っている人がいます。そんな仲間や友人の困りごとなら、自分事として取り組むことができる。「あの人のために自分ができることはなんだろう」という体験から、新しい仕組みやシステムができていくのだと思います。
熊谷:
「まずは自分のために作った」ということに感銘を受けます。ニーズドリブンというか、必要性に引っ張られて技術開発や研究が進んでいくというのは、私も非常に大切だと思っています。
最近、欧米などを中心に「障害者ドングル(disability dongle)」という言葉が使われていることを知りました。これは、社会環境を当事者の慣れ親しんだ方法にフィットするものへと変えるのではなく、求められてもいない技術を障害者側にアタッチすることで、社会環境側を改変することなく問題解決を図るアプローチを揶揄する言葉なのだそうです。
例えば、「螺旋階段を登れる電動車いすを開発しました」とか「目の不自由な人のために、AI技術を搭載した白杖を開発しました」といった技術開発に対して、時として当事者は「わざわざそんなことをしなくても、エレベーターを設置してくれればいいです」とか、「点字ブロックがあれば充分ですし、何もついていないプレーンな杖の方が慣れているので良いです」といった感想を抱くのです。
ここで問題になっているのは、障害者の問題を解決しようとしているのに、技術開発の設計プロセスに障害者の意見が反映されていないということです。ニーズではなくシーズドリブンとでも言うのでしょうか。いずれにせよ、誰かを助ける技術開発が、自分や身近な人、具体的な誰かの必要性にドライブされているというのは大切なことだと思います。
身体のファッション化?
熊谷:
もう一つ、最近知った言葉に「逆チューリングテスト」というものがあるんですけれど、ご存じですか?「相手が(機械ではなく)人間かどうか」を人間が確かめるチューリングテストに対して、これは「相手が人間かどうか」を機械が確かめる様子を表した言葉です。
先日ファミリーレストランに行ったら、私のところに配膳ロボットが来たんですよね。そこで配膳ロボットに「私は人間である」ということを認識してもらう必要があったのですが、これがすごく大変で。似たような事例に、自動運転車が車椅子ユーザーを人間として認識できるか、といったものもあります。
ロボットが生活圏の中に普及してくると、私は彼らに対して自分が人間であることを証明し続けなければいけないという、新たなプレッシャーを課せられそうだなと感じることがあります。
長い歴史の中で、障害者は「人間か、人間ではないのか」といった境界線に置かれる経験を何度もしてきました。ロボットに限らず、あらゆる技術が逆チューリングテストを行っています。生活の中に浸透している技術の設計にも、「何をもって障害とするか」という考え方が現れているのですよね。
オリィ:
こういった問題に対して、逆に、多様な姿、多様な身体の「ファッション化」を狙うのはどうでしょうか。車椅子や服、身体をテクノロジーでさまざまに変容させて、ロボットがパッと見で人かどうか判断できないような人を増やしていくアプローチです。
現在であれば、「スカートは女性」「ズボンは男性」といったシルエットに関するスティグマは、かなりハックしやすくなっているのではないでしょうか。その意味で、車椅子はまだ、「ズボンは男性のもの」といった固定観念と同じくらい「障害者の乗り物」といった見方がなされていて、良い意味でファッション化されていませんよね。
熊谷:
状況を逆手に取るというか、とても強気で面白い戦略です。確かに、どうやって人間らしくロボットに対して存在証明をしようかと悩むより、どんな見た目だって良いじゃないかというアプローチの方が、もしかしたら早いかもしれませんね。
オリィ:
海外の記事で、車椅子ユーザーの人たちが、ハロウィンの日にマッドマックスみたいな乗り物に乗っている様子を見て、そういうのがもっと広がったら良いなと思うことがあります。格好良くて、思わず乗りたくなるような車椅子があっても良いですよね。
昔、車椅子を改造していたら当事者じゃない人から「車椅子で遊ぶとはけしからん」と怒られた
そう思うのは勝手だが、私は車椅子を特別なものと思っていないのでバイクや車のように改造する車椅子は格好いいしもっと楽しくできる
将来寝たきりになっても視線とか自分の意思で姿勢を変え、走り回るのだ pic.twitter.com/7znRQjwATl— 吉藤オリィ@寝たきりの先をつくる (@origamicat) February 5, 2020
「参加」の多様性を変えるかもしれない
——障害とテクノロジーの関係について、お二人の個人的なエピソードはありますか?
熊谷:
Zoom会議の登場には非常に助けられています。移動することなく、どこにいても誰とでもすぐにミーティングができるのは、生活を劇的に変えてくれました。他にも、本棚から物理的に持ち出すことなく、わざわざ机の上で開かずとも、スマホやPCで文献を読むことができるのは、私が学生だった頃には考えられないことです。身体の都合上、私は本を読むことにすごく苦労をしてきたので、これも生活を劇的に変えてくれたと思います。
オリィ:
私は不登校という経験をした時に、物理的なこの世界では社会に参加するハードルがとても高いと感じました。ひきこもり状態にあったので、人と話すこと自体がストレスになっていたわけです。当時暮らしていたのが小さな村だったので、村人たちに声をかけることも、かけられることもストレス。そんな状況でわざわざ学校まで通わなくてはならないのは苦痛でした。
当時「参加」とは「肉体を現地に運ぶこと」だったわけですが、本当にそれしか参加の方法はないのかと、ずっと考えていて、どこでもドアが欲しくてたまらなかったですね。学校に行かければいけないのは間違いないとは思っていましたが、とにかく「外に行く、外を歩く」ということをしたくありませんでした。
もし自分にもうひとつの身体があって、それが学校のロッカーの中に掃除用具と一緒に入っていて、自宅からそこへと意識を飛ばして、ロッカーから「ガチャ」っと出て行けたら……。何食わぬ顔で教室に入って、席に座って授業を受けて、授業が終わったらロッカーの中に戻っていく。そうすると意識が自宅に帰ってくる。そういうものがあったら良いなと小学生の時から妄想していました。
私のように、人からどう見られるのかが過度に気なってしまう人にも優しいコミュニケーションスタイルとして、「参加」の手段はもっと多様になっても良いと思います。
——メタバースと障害について考える際、「参加」というものがどんな方法、どんな形態で実現するかは重要なテーマになりそうですね。
熊谷:
私たちも差別に関する研究を行う中で、「参加したいのに参加させてくれない差別」と「参加したくないのに参加させられる差別」という、二つの差別を解決しなければならないとよく感じています。「同化させられる差別」と「排除される差別」ですね。
私のように、パッと見てすぐに気付かれるような身体特性の人は「参加するな」と言われやすい。しかし外から見てもすぐには分からない「普通」に見える当事者は、本当はいろいろな事情があって苦しいのに、無理やり参加を強いられる。参加したかどうかを聞かれて歯切れの悪い返事をした時に、頭ごなしに「参加したくないんだね」と断定されることが多いのですけど、それもちょっと違うなと思います。要は「適度に参加したい」というニーズがあります。
そこでは情報量や本人への負荷が多くもなく少なくもない、インプットもアウトプットも「適度」にできる参加の形態が望まれています。参加の形態がひとつしかない場合、「それならしょうがないから撤退するか」となってしまう人は結構多いのではないでしょうか。
オリィ:
既に一部実現していることだとは思いますが、メタバースも今後、これまで「参加」できなかった人の「参加」を可能にする、新しい選択肢になることを期待しています。
熊谷:
本当にその通りですね。他方で逆に、大学の授業が一斉に「Zoom化」した時、参加できる人とできない人の分布が変わったような気がしていて。オンライン授業は、さまざまな事情で参加できなかった人の参加を劇的に増やした一方で、今度は思いもよらないところで参加できなくなってしまった人を生み出してもいるかもしれません。
以前なら、私みたいな人はとにかく授業に参加しにくい状況でした。身体が動かないとか、あるいは他にも社交不安障害があるとか。しかしいまでは、小さな画面を集中して見続けるのが苦痛だという人は参加しづらいだろうし、聴覚や視覚に障害を持つ学生さんがアクセスできる情報も大きく制限されてしまっている。
——2020年以降、いわゆるZoom疲れ(Zoom Fatigue)は学術領域でも盛んに議論されていますよね(例:Bailenson, 2021)。リモートでの生活を強いられたことで、社会に「スタンダード」だとされるスタイルに対する息苦しさを初めて覚えた人も多いと思います。
熊谷:
もし仮に「参加したいのにできない人」のことを障害者と呼ぶののであれば、世の中の「当たり前」がオンラインになったことを受けて、障害者の定義がガラリと変わってしまったのだと思います。一瞬の環境の変化によって、こうもあっという間に変わってしまうのかと。
おそらく大切になるのは、参加の手段をどれだけ冗長化し複数的に確保し続けることができるか、だと思います。これしかない、というのではなく、常に複数の参加の方法が確保されている冗長な状況を保つことです。
オリィ:
私は昔からオンラインゲームが好きで、友達もいるし思い出もある。そこで充分「生活」できるな、と思ったこともあります。しかし例えば歳をとっておじいさんになった時に、「外に行けないならVRで我慢してね」と言われ、強制されてしまったら——友人がみんな現地でお花見に行っている時、自分だけVRでお花見をするのだとしたら——それはちょっと寂しいなとも思いました。
——複数の選択肢が常に開かれていること、それらのうち好きなものを選べることは大事ですよね。
オリィ:
私は、実は大学を卒業していないんです。授業を4回程欠席すると単位をもらえないという制度があり、体調を崩しがちで通学が難しい時期もあった私は単位を取りきれなかったからです。「Skypeでいいじゃないですか」と抗議もしましたが、当時はまったく認められませんでした。
その時に悔しくなって作ったのが、スキャンした私の顔のシリコンマスクを搭載した「ケンタロイド」という分身ロボットです。これを私が遠隔操作して、先生が何か言うたびに一番前の席で頷いて、音声通話で質問をしました。
まだzoom出席など無かった大学時代、体調を崩し休みがちで単位が危うかったが私そっくりの分身を作ってリモート出席&積極的質問し「これでダメなら出席とは何なのか」と言いまくった結果、出席を認めさせたりした。2011年の事だ
世の中の理不尽、時代遅れなルールにはテクノロジーをぶつけていけ pic.twitter.com/YlUsmZlE6d”>pic.twitter.com/YlUsmZlE6d
— 吉藤オリィ@寝たきりの先をつくる (@origamicat) November 28, 2021
オリィ:
「これで出席点がもらえないなら、身体とは何なのか」と言いまくった結果、出席点をもらえたという実績があるロボットです。先に申し上げた小学生の頃の妄想——ロッカーにしまってあるもうひとつの身体を通じて授業を受け、授業が終わったらその身体でロッカーに戻って行く——が実現した瞬間でした。
身体を教室に運んできているけれども寝ていて意識がそこにはない生徒と、身体は分身だけれども最前列で熱心に話を聞いている私。どちらの方がより「出席」したと言えるのでしょう。これを通じて思ったのは、「参加」とは相手が自分を認知していること、そして自分自身もそこに存在している実感があるということの二つが満たされて成立するということです。
ただ、既に参加の方法はさまざまに登場してはいるものの、現時点ではまだ学校の先生の都合やシステムの都合で、ZoomならZoomだけ、対面なら対面だけ、と片方だけになってしまいがちです。冗長な参加方法が担保されているハイブリッドでの運用が難しい。Zoomや対面、OriHime、メタバースとそれぞれのルートはあっても、それらすべてに同時に、同等のコンテンツや体験を提供するのは難しいですよね。
熊谷:
全くその通りだと思います。「ハイブリッドが良いに決まってる」といって教育現場での運用が始まっても、最終的にしわ寄せが来るのは現場の教員ですからね。誰かに負担が集中することなく、複数の参加形態を運用するという課題は、どんな解決策があり得るのかぜひ知りたいです。
「居場所」の条件とは何なのか?
熊谷:
参加という話をもう少し広げて、私は最近、所属感や帰属感に興味を持って研究を始めています。そのきっかけとして知ったのが自殺の研究です。どういう条件が揃ったら人は自殺をしてしまうのか。自殺の対人関係理論では、「痛みの知覚に慣れてしまうこと」「自分の存在が大切な人や社会の負担になっていると感じること」、そして「どこにも所属していない、誰からも受け入れられていないと感じること」が自殺につながると説明されています。
近年ダイバーシティやインクルージョンへの注目が高まっていますけれど、インクルージョンの定義の中核にこの「所属感」を置きましょうという流れがあります。そこに所属していると当人が感じられるかどうかは、ひとつの大切な試金石です。ここまでの「参加」の話と、この「所属感」の話は、どこかでつながりそうな気がします。そしてメタバースやロボットとの共生など、テクノロジーが生活を変えてしまうことに対する抵抗感を示す人がいるとしたら、「自分はそこで、主体的に参加している感や所属感を得られるのだろうか」という不安があるのかもしれません。
オリィ:
所属感とは、そこを居場所であると感じられるということでしょうか。
熊谷:
「居場所」という言葉もさまざまな文脈で多義的に使われるので断定は難しいのですが、私は、「思い出」という表現がピンと来るんですよね。所属感が生起する条件として、共同作業や思い出の共有は重要です。一緒に何を成し遂げることやその思い出の共有、あるいはお互いの物語を知ってる状態とでも言うべきでしょうか。トータルな自分のストーリーを共有できている人が周りにいることは、所属感の重要な要因だと言われています。
そういう意味では、単に仕事上の関係しかない、自分の物語を知ってる仲間が少ない職場には、所属感を感じにくいかもしれません。
オリィ:
仕事関係の思い出だけではなく、ということですね。
熊谷:
そうですね。私が取り組んでいる当事者研究でも、身体と物語という二つの側面を重要視します。当事者研究は、唯一無二の自分の身体と、唯一無二の自分の物語(思い出)、その二つを自分自身で振り返り、他者と共有し共同編集をしていく作業です。まだ議論をしている最中で答えは出ていないのですが、「トータルな自分」を仲間と共有することが、所属感やそのコミュニティに参加している感じを高めているのではないかと考えています。
「コミュニケーション」のさらなる先へ
オリィ:
逆に自分が居場所を感じないコミュニティでは、自己開示をしにくいということもありますよね。
熊谷:
そうですね。信頼がない感じというのでしょうか。怖いですもんね。
オリィ:
関係性作りというのは、私の中で一番のテーマになっています。だから私は、自分が開発している技術を「コミュニケーションテック」ではなく「リレーションテック」と呼んでいます。アグリテック(農業における技術)やフィンテック(金融における技術)など、さまざまな〇〇テックという言葉が生まれましたが、我々が取り組んでいるのはコミュニケーションというよりリレーション(関係)。その場所に入って、周りの人たちと会話することで、どんな関係性を築けるか。身体が動かなくなってしまった後でも、居場所や友人を作ることのできるテクノロジーです。
熊谷:
コミュニケーションとリレーションの違いについて、もう少し詳しく教えていただけませんか?
オリィ:
テクノロジー(テック)の部分も定義が広いですが、いずれにせよ、自分達はテクノロジーそのものを目的にはしていないなとは思っています。テクノロジーは何かのための手段だとすれば、ではコミュニケーションは目的なんだろうか、自分たちが作っているのはコミュニケーションテックなのか、と。
そのように考えていく中で、我々にとってはコミュニケーションも手段であって、コミュニケーションを通して実現したいゴールが別にあることに気づきました。私が掲げているミッションは「孤独の解消」で、それが達成されたゴールこそ、先ほど話題に出た所属感とか居場所を作ることだと考えています。
自分の居場所がどこにもないという感覚、自分は誰からも必要とされていないという状態から復帰できること、誰かと何かを一緒にやっていられる状態を作ること、そのゴールのためのテックが「リレーションテック」です。
熊谷:
オリィさんの活動目的が極めて明確に示されていますね。私たち人間には目的と手段を間違えてしまい、手段が目的化しやすいところがあります。先ほど挙げた「障害者ドングル」という言葉はテクノロジーが目的化してしまった状態を揶揄しているわけですが、オリィさんの活動には一貫して「孤独の解消」という目的が据えられている。
オリィ:
一点だけ補足をすると、私たち(オリィ研究所)は孤独の解消を目的に対してテクノロジーやコミュニケーションを手段としているけれども、逆にテクノロジーやコミュニケーションそれ自体を目的として追求する人がいても全く構わないと思います。
メタバースにしても、それが手段なのか目的なのかは、人によって違っていい。手段として活用している人と目的として追求している人が、一緒に組めることもあるはずです。テクノロジーが手段であるというのは私のスタンスであって、一般にそうあるべきだという話ではないと思っています。
熊谷:
一人一人が何を目的にするかは、自由の根幹に関わることなので、そこの統一を強いるのは本当に問題になりえますよね。社会全体のレベル、組織のレベル、プロジェクトのレベルなど、レイヤーごとに目的を整理してしていく必要がありそうです。
——OriHimeというアバターの持つ絶妙な「匿名性」の話も伺いたかったのですが、非常に名残惜しいことにお時間が迫ってきてしまいました。
熊谷:
匿名性というキーワードが出たら、あと一時間は話さないといけないですね(笑)。
——また機会がありましたら、ぜひ続きの議論も聞かせてください。最後に、これから「メタバース」の開発や推進に携わっていく人たちに、メッセージをお願いします。
熊谷:
今日は短い時間でしたが、すごく楽しかったです。参加や所属感、障害といった主題は、冗長な技術によって手段の目的化が起きやすいと感じます。個人というよりは社会というレイヤーの話になりますが、それを防ぐために、目的と手段を整理してさまざまな活動を位置付けていくことが重要になりそうです。他方で、オリィさんが最後に仰った通り、一人一人のモチベーションや自由にどんどん突き抜けていくことも同じくらい重要だと思いました。
オリィ:
障害による困りごとというのは、当事者ごとに全然違っています。同じ脊髄損傷でも、人によって抱えている悩みは違う。それぞれに違う困りごとは、その人と知り合いになると、自分事として一緒に考えられるようになります。あの人が困っているのだったら、私の持てる力で何かできないだろうか、と一緒に考え始める。
メタバースは、出会える人の幅を大きく広げてくれるでしょう。住んでいる場所も、使っている言葉も、持っている思想も違うさまざまな他者と出会えるようになる。そうなった時、そこでも困りごとの共有、自分事化、一緒に考えること、そして誰かの役に立つことができるようになる。そうしたことがたくさん起きると、少しずつみんなが参加しやすい場所へと進化していくのだと思います。
自分らしさとは、選択肢を持っているということです。選択肢としてのメタバース、居場所としてのメタバース、そういう未来を一緒に作っていければと思っております。本日はありがとうございました。
(聞き手・執筆:yunoLv3、編集:水原由紀)










