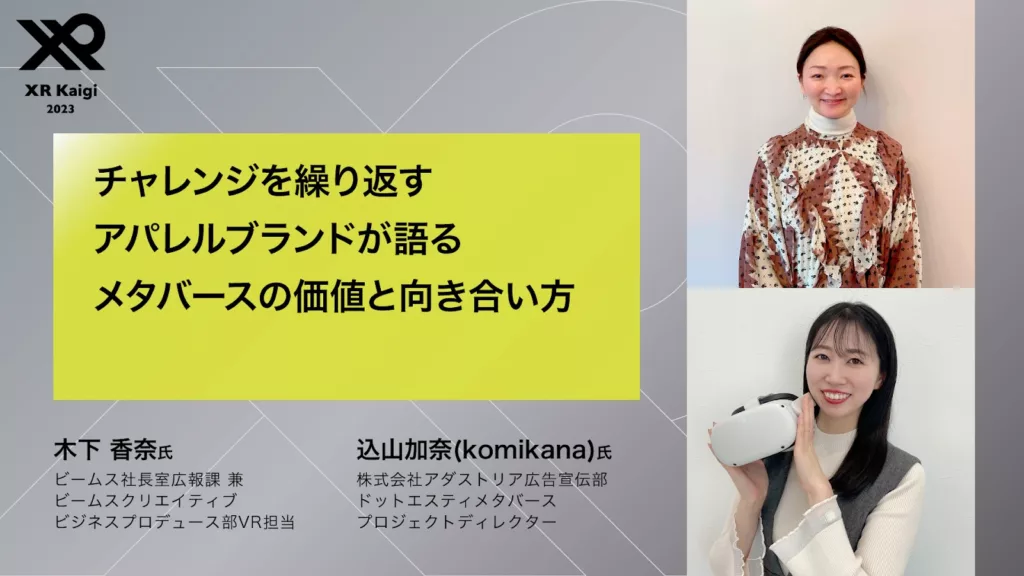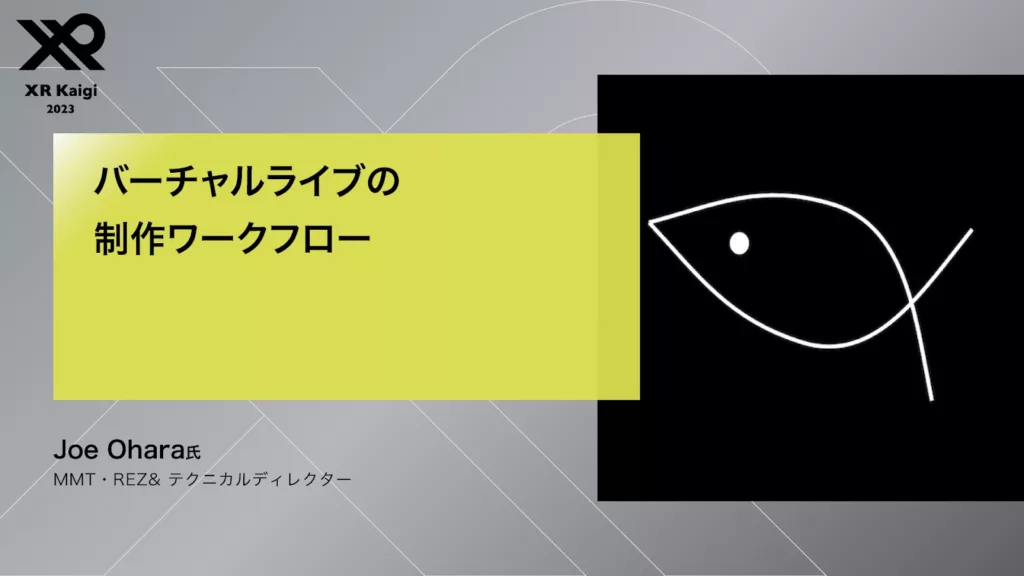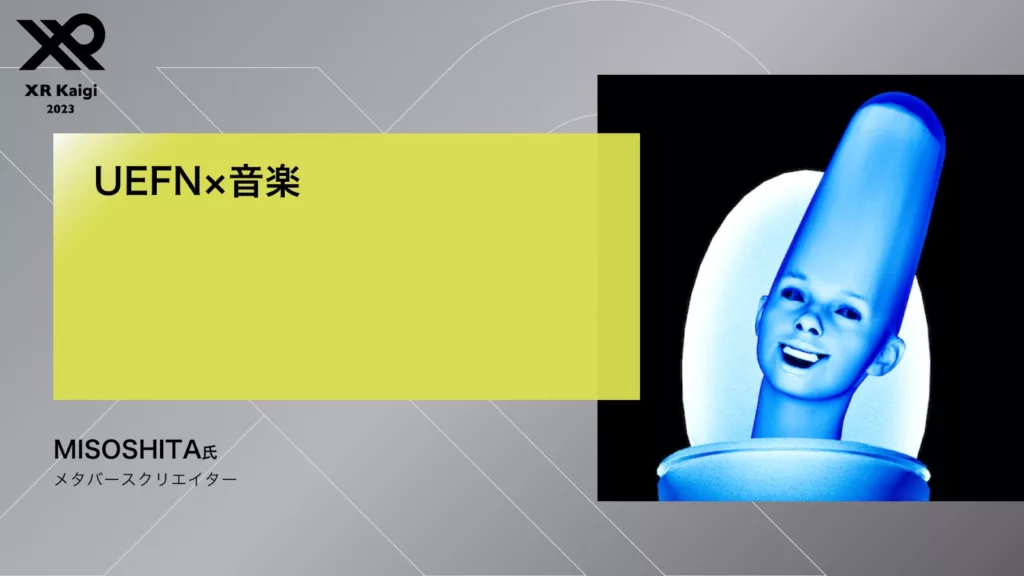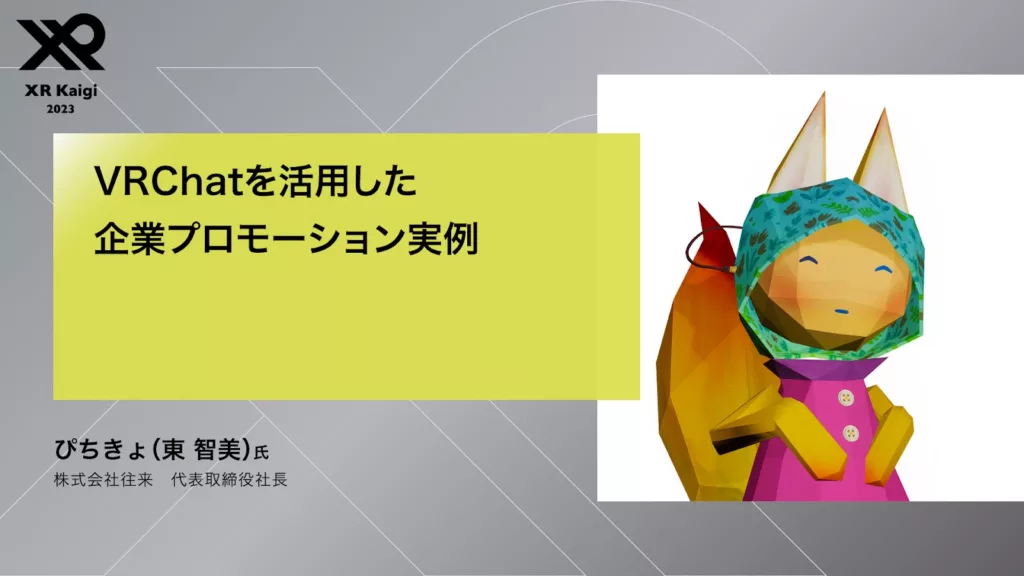60以上ものセッションが開催される、XR/メタバースがテーマのカンファレンス「XR Kaigi 2023」。本記事では、その中から5つのセッションをピックアップしてレポートします。
目次
1.VRヘッドセットは何歳から使えるのか? 「13歳問題」について:エンターテインメントXR協会
2.交流型メタバースで求められる「バーチャルファッション」の世界:アダストリアxビームス
3.バーチャルライブを実施するうえで重要なのは「安定感=没入感」:MMT・REZ&
4.作曲ツールとしても使える「フォートナイト」から、ミュージシャンが生まれていく:MISOSHITA
5.メタバース活用は「ワールドを作るだけ」ではない、コミュニケーション施策や継続を:往来
VRヘッドセットは何歳から使えるのか? 「13歳問題」について:エンターテインメントXR協会
VRコンテンツやサービスを提供している方、あるいはこれからVRに取り組むつもりの方は、セッション「『13歳問題』の現況と協会ガイドラインについて」をチェック。一般社団法人エンターテインメントXR協会の代表理事、安藤晃弘氏のセッションです。VRにおける年齢制限について、最新の状況をチェックしてみましょう。
安藤晃弘:
まず「13歳問題」についてご紹介しましょう。VR元年と呼ばれた2016年頃、VRヘッドセットの年齢制限は、メーカー側からは定義されていない、もしくは「12~13歳以上」に制限されている状況でした。当時は「HTC VIVE」に「PlayStation VR」、そして「Oculus Rift」が登場した年で、一般の家庭でもVRが体験できる状況になりました。当初、HTCは「子供の利用は不可」、ソニーは「PlayStation VRの対象年齢は12歳以上」、Oculusは「13歳未満の子供は使用してはいけない」と表明していました。ここから「13歳問題」が生まれました。
安藤さんいわく、VRヘッドセットのメーカーによって年齢制限に違いがあり、提供者も体験者も迷いが生じやすい状況だったとのこと。その後、ゲームセンター等の施設型エンターテインメントに携わる人々の中で「業界としてガイドラインが必要だ」との声が上がり、2017年に「ロケーションベースVR協会」が発足。現在は「エンターテインメントXR協会」に名前を変え、活動を継続しています。
安藤晃弘:
眼科医など有識者から子どもの立体視への影響を調査したり、様々な文献を見て、以下のガイドラインを策定しています。・13歳未満のお子様に両眼立体視機器を利用した施設向けVRコンテンツを利用させる場合、下記の注意事項について保護者に同意を得たのち、保護者の責任でご利用ください。
・7歳未満のお子様にはご利用させないでください。
・VRコンテンツの内容について、保護者がふさわしくないと判断されるものはご利用させないでください。
・VRコンテンツのご利用時間について、連続20分のご利用に対し、10分から15分程度の休憩を取ってください。
・斜視や複視、その他、視力の異常や眼科的疾患のあるお子様や眼科に通われているお子様は、専門医に相談の上、ご利用ください。
・ご利用後にお客様のお子様の視力について異常が見られた場合、早急に専門医を受診してください。
では、なぜ「7歳以上なら、保護者の同意を得たうえで体験できる」というガイドラインになったのでしょうか。
安藤晃弘:
この質問に対して、エンターテインメントXR協会としては、「一般的に、基本的な立体視の発達は6歳から7歳で終わるとされています。小児科を専門としている医師から『立体視の発達過程である成長期において、その妨げとなる行為を行うことは望ましくありません』との意見をいただき、そのうえで有識者で検討を重ねた結果、本ガイドラインにおいてはこのような自主規制を設けました」と返答しています。
時代とともに、VRヘッドセットの使用に関する年齢制限も移り変わりつつあります。国内外のVR体験施設の状況を調査している安藤さんに、最近のトピックも教えてもらいましょう。
安藤晃弘:
施設で使うデバイスはHTCのものが主流でしたが、最近Metaのデバイスを良く見るようになってきました。海外の「The INFINITE」という施設では「Meta Quest 2」を使っており、8歳以上は保護者の同意がなくてもよいという形になっていました。HTCが台湾で展開している「VIVELAND」は6歳からの体験が可能となっているようです。
交流型メタバースで求められる「バーチャルファッション」の世界:アダストリアxビームス
続いて「チャレンジを繰り返すアパレルブランドが語る メタバースの価値と向き合い方」からレポートをお届けします。2021年ごろより「Roblox」や「フォートナイト」など、いわゆるゲーム中心のメタバースだけではなく、「cluster」や「VRChat」といったコミュニケーション主体のメタバース(あるいはソーシャルVR)においても、バーチャルファッションが盛り上がっています。
Robloxは2022年・2023年と続けてデジタル上でのファッション&ビューティ・トレンドレポートを公開。「デジタル上での、自分らしさの表現の重要度はさらにアップ」「メタバースにいるZ世代にとってブランド認知が重要」としており、年々市場規模は拡大、注目度やカルチャー的な重要度も上昇し続けています。
本セッションでは、VRChatをはじめとしたメタバース向けのバーチャルファッション制作・販売に取り組んでいるビームスの木下香奈氏、株式会社アダストリア(.st)の込山加奈氏のお話から、日本国内のアパレル企業がメタバース市場にどうチャレンジしていくかのヒントを得ていきましょう。
さて、お二人がメタバース市場に取り組んだのはいつごろからなのでしょうか?
込山加奈(アダストリア):
アダストリアでは、2022年7月にメタバースプロジェクトを立ち上げました。2023年3月には3DCGクリエイターが入社、自社で3Dアイテムを制作することが可能な環境となり、1.5~2ヶ月のスパンで新作を発売しています。木下香奈(ビームス):
ビームスは2020年からバーチャルマーケットに参加しています。イベント中は弊社のスタッフがバーチャル接客を担当し、バーチャルとリアルの交差点でいかに楽しいことができるかということを常に考えています。また2023年2月からは「ZEPETO」でもコレクションを発売しています。
お二人は同業かつメタバースにチャレンジしているという共通点があると思います。どのようにコミュニケーションを取っているのでしょうか。
木下香奈(ビームス):
はい。リアルのアパレル企業で、バーチャルでも色々やってる企業ってまだまだ少なくてとても近いところにいますので、VRChatの中でも一緒に遊んだりしてますね。込山加奈(アダストリア):
そうですね。去年の年末とかはバーチャルでプチ忘年会を開催したりしました。
どうやら私生活含めてメタバース/バーチャルファッションを楽しんでいるご様子。さて、メタバースへの取り組みを始めたとき、社内からの抵抗や否定的な反応はなかったのでしょうか?
木下香奈(ビームス):
私たちの場合は、最初に社長が「メタバースをやりたい」と切り出したところからスタートしています。ビームスらしい企画で、ビームスがやる意味をどういう風に見出していくかを考えました。メタバースがバズワードになった時期は、いろんな部署から興味を持ってもらえたので、実際にバーチャル接客を体験してもらったところ、好意的な反応をいただいてきました。本当に「実践あるのみ」です。込山加奈(アダストリア):
アダストリアでも、メタバースというキーワードはすごくアップトレンドでした。その流れで「.stの公式ウェブストアで、新規顧客との接点が得られるのではないか」という意識からスタートしています。ありがたいことに、最初から経営陣も含めて応援してくれました。プロジェクトが始まってから約1年半ですが、 そもそもアダストリアに「挑戦する」社風があり、活動しやすい環境だと感じています。
自社ECサイトへの送客を意識しているアダストリアさんと、実店舗への送客を見ているビームスさんですが、俯瞰してみると取り組み方に違いがあるように感じます。
木下香奈(ビームス):
ビームスの場合は、セレクトショップという業態上、カルチャーやライフスタイルという切り口から、ファッションアイテムやトレンドを紹介してきました。その延長線上で、バーチャル/メタバースも、1つのカルチャーやライフスタイルとして紹介しています。ですので、バーチャル店舗を出して、バーチャル空間にいる方々と交流しながら、私たちが持ち込んだものがどう受け取られているかを見つつ、半年ごとに取り組みをアップデートしています。込山加奈(アダストリア):
我々はマーケティング本部に所属していることもあり、お客様のニーズをかなり深掘りしてからスタートしました。自分たちが実際にバーチャルファッションを作り始めてから、この世界はクリエイターの方々の手で作り上げられている、と感じました。リアルだと友人やモデル、ファッショニスタに憧れて洋服を購入するように、アバターが着ているお洋服がおしゃれの参考になるんじゃないかな、と。そこで「◯◯というアバターが着ているから洋服が欲しいな」という流れでご購入に至る可能性を考えて、まずはアバターを作ることにしたんです。
いままでのことを振り返ってみて、どういった変遷があったかも知りたいところです。
込山加奈(アダストリア):
3DCGデザイナーが入社したことで、自社でバーチャルファッションを制作できるようになったことに加え、デザイナー自身がワールドも作れるので、活動の幅がより広がってきました。社内にデザイナーがいるといないとでは、全く違います。コミュニケーションの部分でもすごく大きいですね。もちろん外部のクリエイターさんとお話しすることで、新しい知識やインスピレーションを得ることもあります。ですが、デザイナーが社内にいることで、すぐに分からないことを聞けたり、スピーディーに物事が動くようになったと思います。木下香奈(ビームス):
私たちはセレクトショップなので「いろんなブランドを仕入れる」という発想で動いています。ビームスには、オリジナルブランドの他にもいろんなブランドを取り扱っていますから。なので、自社で何かひとつを強く打ち出すというよりも、クリエイターとコラボレーション等を通してファッションアイテムを生み出し、それを紹介していく。なので、私たちは3DCGデザイナーを社内に抱えるよりは、いろんな方と一緒に広げていく方向で発展させていきたいと思っています。
バーチャルライブを実施するうえで重要なのは「安定感=没入感」:MMT・REZ&
次は「バーチャルライブの制作ワークフロー」で登壇されたMMT・REZ& Joe Ohara氏のお話を見てみましょう。Ohara氏はバーチャルライブ制作のテクニカルディレクター、そしてライブや展示などのエンジニアを務めています。
MMT・REZ&は、映像プロダクションMMTとビジュアルアートチームREZ&の2社によるクリエイティブチーム。「現実側のライブ現場での知見を生かせれば」と考えながら、多数のバーチャルライブ制作に携わってきました。
バーチャルライブのワークフローには、いくつかのスタイルがあるそうです。
Joe Ohara:
一つは「収録型」です。歌もモーションも事前に記録しておき、「Unreal Engine」や「Unity」、その他CGソフトなどを用いてレンダリングをし、ライブを行う形になります。続いて「半収録型」。難易度の高いダンスや歌唱パートは事前に収録し、MCなどはリアルタイムに行う形です。最後に「リアルタイム型」。こちらは文字通り、すべてリアルタイムで行います。
「このスタイルが一番優れている」といった優劣は特に存在せず、バーチャルライブの企画が始まった段階で、その内容に合わせたものを選んでいるそうです。
Joe Ohara:
企画の性質によって必要な要件が変わるため、ディレクター、テクニカルディレクター、プロデューサー、クライアントを交え、たくさん議論をして決定します。この決定によって制作方法が大きく変わってくるため、慎重な判断が必要です。このバーチャルライブは配信なのか、現地ライブなのか、どのようなフォーマットで出すか、どのような配信プラットフォームで配信をするか……などなど、クライアントやアーティストさんから、どの部分を特に注力をするかを探っていきます。また演者は何人出るのか、どのようなスタジオで収録を行うかなど、様々な要件が出てきます。
「リアルタイムでやりたい」「多くの演者を出したい」という要望があるときは、それに耐えうる空間の制作や、モーションキャプチャスタジオの選定などを行っていきます。照明やエフェクトをどれくらい詰め込むことができるのかなども、この段階で決まっていくとのこと。
Joe Ohara:
実際に作る時は、処理の安定性の確保が最優先です。「スパイク」と呼ばれる、瞬間的に処理が高まった際に起きる処理落ち、そしてフレームレートの低下は、ライブの没入感を大きく下げてしまいます。制作が始まる前に懸念要素をできるだけリストアップし、 ディレクターと話し合いながら様々な工夫をしていきます。例えばワールドを切り替えた際の処理落ち対策として、一部だけ事前に収録しておいたワールドのインサート映像に切り替えたり、照明を安定させる、といったテクニックを使っています。
最近ではライブ中のレンダリングには「Unreal Engine」を、制御には「TouchDesigner」や各種VJソフトを活用しているそうです。
Joe Ohara:
構成はライブによって変わりますが、ゲームエンジンであるUnreal Engineは、リアルタイムでレンダリングが行われるため、ライブ制作にとても有効です。開発のスピード感を高く保つこともできます。またUnreal Engineは物理ベースレンダリングを採用しており、実写のような、リアリティのある高品質な空間表現が可能です。また、制御で最も使用しているソフトウェアはTouchDesignerです。ノードベースのビジュアルプログラミング環境で、MIDIコントローラなどの外部デバイスや各種通信プロトコルなど様々なものに対応しているため、映像や制御信号の入出力などを簡単に行うことができます。
それ以外のソフトウェアでは、 モーションキャプチャーデータの調整からUnreal Engineへの送出に「MotionBuilder」、楽曲に紐づいた演出信号の送出や、PAさんが出してくれるタイムコードと同期したエフェクト再生用にMIDI/OSCシーケンサの「Vezer」などを使っています。
開発が必要な制作フローは、フェーズ1として「ワールド制作とキャラクター調整」、フェーズ2として「フェーズ1をベースとしたライト、カメラ、エフェクトなどの制作」を行い、最後に「ライティング、VJ、スイッチング、モーションを組み合わせてライブを完成させる」そうです。
Joe Ohara:
我々のチームでは、企画ごとに新たな取り組みをするためにR&D(研究開発)を行っています。例えばワールド内に配置したオーディエンスの3Dモデルを、その場で再生される音楽に乗せて動かし、盛り上がっている様子を表現する「オーディエンスジョッキーシステム」。TouchDesigner上でモデルのアニメーションの切り替えやスピード調整、あらかじめ配置したグループごとにモーションの制御を行います。こうした研究開発や実装を行うことで、表現の幅を広げることもでき、さらにチームとして成長することにもつながります。
作曲ツールとしても使える「フォートナイト」からミュージシャンが生まれていく:MISOSHITA
巨大ゲームプラットフォームであり、「メタバース」でもある「フォートナイト」は、対戦ゲームだけではなく、コミュニティスペースやバーチャルライブ会場・プラットフォームとしての側面もあります。今回はメタバースクリエイターのMISOSHITA氏に、「UEFN×音楽」というテーマで、フォートナイト上での音楽鑑賞イベントの作り方を解説していただきました。
なお「UEFN(Unreal Editor for Fortnite)」とは、Unreal Engineをフォートナイト用にカスタマイズした専用のエディターツール。独自のプログラミング言語Verseを使用可能、外部のアセットなどを読み込むこともできるため、クオリティの高いものが作れるようになっています。
MISOSHITA:
現在、フォートナイトの音楽領域は「音楽鑑賞をするところ」から「ゲームで遊びながら音楽を楽しむ」形式に変化していると思っています。以前はメタバース上で何かパフォーマンス演出を見るというものだったんですが、そこに「スコアを稼ぐ」「出てきた敵を倒す」というようなゲーム体験がプラスされて、鑑賞でなく参加型・体験型に変わってきています。
数年前の「XR Kaigi」でも、「バーチャルインタラクティブミュージック」を提唱していたMISOSHITAさん。今回はその発展形であるワールドを作成し、その制作過程を紹介しました。
MISOSHITA:
音楽はフォートナイトの中心となるコンテンツではありませんが、フォートナイトのカテゴリに「ミュージック」があるように、少なくとも一定の需要はあるのではないかなと思っています。やはり5億人もユーザーがいるプラットフォームなので、「一定の需要」だとしても、かなり大きな数字が期待できると考えています。
では、実際にUEFNで表現できる音楽まわりの機能を見ていきましょう。
MISOSHITA:
まず「ラジオ」という機能ですが、これは音楽ファイルを再生する音楽機能です。これをベースに、ゲームの状況に合わせてBGMを切り替える、音を消す、といった表現ができます。他には「シーケンサー」もあります。これは音だけではなく、ビジュアルも同時に制御できるようになっています。ビジュアルの演出と音の演出を同時につけられることから、バーチャルライブを作るときには重宝します。
基本となる機能のほかにも、演奏の要素を含めた機能も。
MISOSHITA:
「ミュージックブロック」も面白い機能です。画面内に配置されるブロック1個1個に、音程と音色を割り当てられます。また「パルストリガー」機能は、テンポを設定して音を鳴らしていくもので、UEFNでオリジナルの音楽制作が可能になっています。「パッチワーク」機能は、フォートナイトのマップ内でリアルタイムなドラム、ベース、メロディパートの制作、編集、演奏が可能なデバイスです。簡易的なDTMアプリのようなイメージですね。見た目はシンセサイザーなどのようなデバイスになっています。
最後に、UEFN×音楽の可能性についてのお話をうかがいました。
MISOSHITA:
フォートナイトの可能性として、フォートナイト内での音楽を含めたIP展開の価値は十分にあると思っています。ユーザーが5億人もいるゲームプラットフォームでありメタバース空間だと考えると、ここからキャラクターやフォートナイト初のヒット曲が生まれる可能性もある。また、インタラクティブな音楽体験の可能性というところで、ただ再生するだけではないような音楽の楽しみ方ができると思います。さらに「手軽に作れる」こともポイントで、フォートナイトから音楽制作を始め、スターになる若い人たちが出てくるはずです。
メタバース活用は「ワールドを作るだけ」ではない、コミュニケーション施策や継続を:往来
最後にご紹介するのは「VRChatを活用した企業プロモーション実例」です。数々の企業や自治体をクライアントに持ち、VRChat内でのプロモーションビジネスを手掛けている株式会社往来の東智美(ぴちきょ)氏のお話を伺いましょう。
東智美:
私たちは社内にクリエイターさんを抱えるのではなく、VRChat内コミュニティのクリエイターさんたちと協業しながらお仕事をしています。まず企業の方からオファーをいただき、プロジェクトの目的に沿ったコンセプトやストーリーをもとにした企画を出して、プランニングをします。制作に入ったら、内容に合わせてタスクフォースを組み、プロジェクトを進めます。
メタバースを活用したプロモーションの制作を請け負う企業は増えてきていますが、東さんの会社は「その先」があるといいます。
東智美:
往来は情報拡散のための広報、イベント運営、ワールドのアップデート企画提案も行っています。これを重ねていくことで、企画そのものを熟成させていきます。「拡散」領域についてはメディアリレーションを得意としています。主にテックメディアが多いのですが、編集部の記者やライターさんと連絡を取り記事を書いていただいたり、SNSを使ったバズを起こすことを中心にしながら話題を広げ、ワールド自体にアップデートをかける、または継続的にイベントをするなどして、長い目で企業のブランディングに繋がる施策を行っています。
東さんが起業したのは2021年。仕事をしていくなかで、直接的なクライアント以外からも「メタバース内に場所を作ったはいいけれど、集客ができない」という悩みを聞くようになり、「コミュニケーションをデザインして集客を行うことが大きなテーマになるのではないか?」と感じるようになったそうです。
東智美:
今までやらせていただいたお仕事の中でも、印象に残っている「コミュニケーションの成功事例」をお話しさせてください。日産自動車さんがEV(電気自動車)の「日産サクラ」を発表する際、VRChat内で日産サクラに乗ってドライブができるというワールドを作りました。厳密なドライブ体験ができるものではなく、あくまで雰囲気を楽しんでもらうというものですが、VRChatでの体験によってサクラを購入した、という方がいました。お話をうかがったら、購入された理由は「VRChatの友達と一緒にドライブした時、すごく楽しかったから」だったんです。自動車は決して安いとは言えない商品です。私は「リアルな試乗体験ができないと、購入する強い動機にならないのではないか」と考えていたところがあったので、これは目から鱗が落ちる思いでしたね。
また、リアルとバーチャル、両方が交わったプロモーション施策となった例もあります。
東智美:
モスフードサービス様の施策では月面にモスバーガーの支店を作り、そこで新商品の月見フォカッチャを作れるコンテンツを組み込みました。友達同士で作った月見フォカッチャを食べているシーンを写真に撮ってSNSでシェアするだけじゃなく、実際にモスバーガーの店舗に行って撮った月見フォカッチャの写真と並べてシェアする方が多くて話題となりました。当時モスフードサービス様は月見フォッカッチャのPR施策としてVRChatのほかにセーラームーンとのコラボ、星街すいせいさんとのコラボと3つの施策を同時に打ったのですが、これがすごく当たり、期間目標であった160万食の半分となる80万食を8日間で売り上げる事態となりました。この中でメタバースが担った役割は大きいという評価もいただきました。
ハイクオリティな3Dアイテムをあえて無料で配布する施策もヒットしました。
東智美:
横須賀市観光課様の依頼で手掛けた自治体のメタバース施策ですが、重要だったのは無償配布した3Dデータの「スカジャン」です。あらかじめもっとも重要な要素となることが分かっていたので、予算を割き、VRChat上で最も人気があるといっても過言ではないクリエイターの方に制作を依頼し、そして横須賀でオリジナルのスカジャンを作られている方に監修をお願いしました。またアンバサダー制度を取り入れ、TikTokなどで動画を公開してもらうことを条件としてデータを先行配布したところ、1週間で1万着、10日で1万5000着のダウンロードを記録しました。人気のアバターに合わせて調整したデータで、多くの人がVRChatだけではなく、cluster用のアバターにも着せてくれて、SNSで多くのアバター自撮り写真をシェアしてくれました。
一度作った場所に何度も訪れてもらうようにするには、ただ単に作っただけで終わりではない、いわゆる「箱物行政」にならないような工夫も必要だといいます。
東智美:
メタバースを使ったプロモーション施策はウェブサイトと一緒だと思っています。しっかり継続してアップデートを行うとか、手を入れることが大事。メタバースの場合はワールドのアップデートも必要なんですけれども、イベントを定期的に開催することでコミュニティに印象を残して継続性のあるものにしていかないと、作っても無用の長物になってしまうのではないかなとは思います。